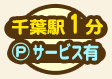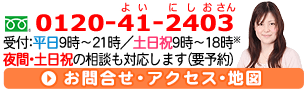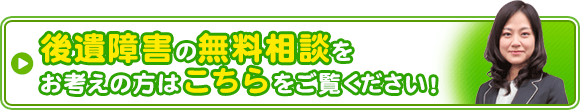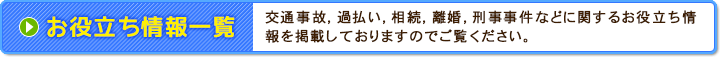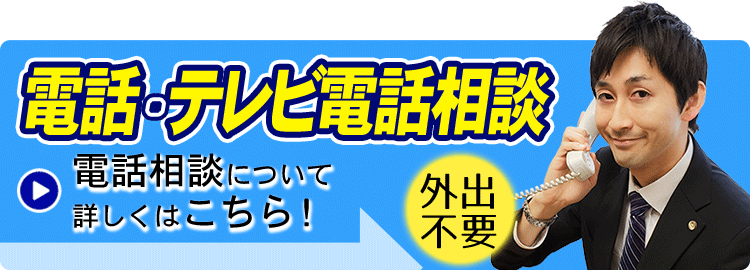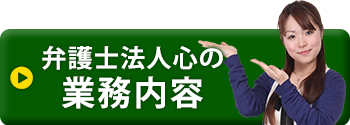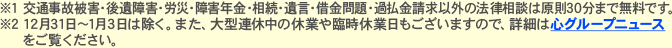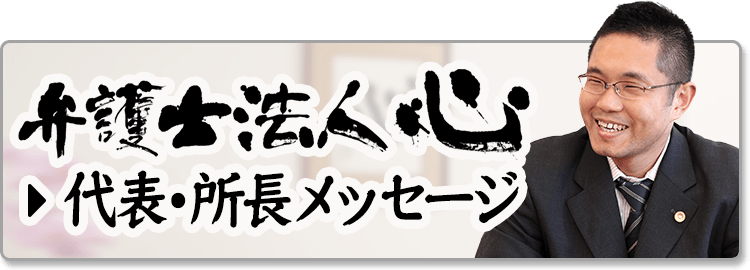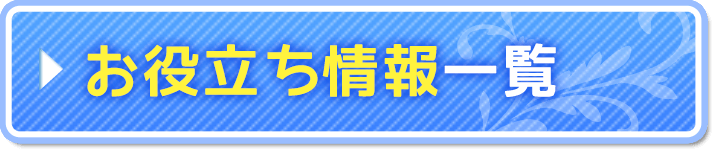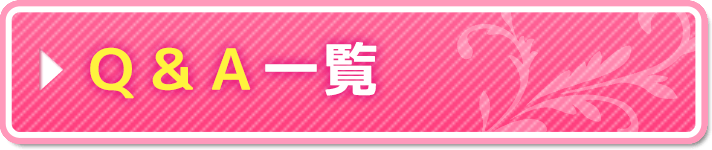非器質性精神障害の後遺障害申請にはどのような特徴がありますか?
1 非器質性精神障害と後遺障害申請の特徴
脳を損傷した高次脳機能障害や骨折などは器質的損傷がある場合には、レントゲンやMRIなどの画像所見があるため、比較的、症状に関する客観的な証拠を得やすい傾向がありますが、そういった器質的損傷が無い=非器質性の場合には、客観的証拠が乏しく、適切な後遺障害等級の認定を受けるために注意しなければならない点が多くあります。
その中でも、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)といった精神障害は、症状が個人によって大きく異なることがあり、かつ、長期で見た場合に治る方や相当程度症状が良くなる方も多いため、適切な後遺障害等級を得るために注意しなければならないことが多いです。
2 非器質性精神障害の後遺障害等級とは
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの」であれば、9級10号になります。
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」であれば、12級13号になります。
「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの」であれば、14級9号になります。
3 早期の受診、早期に症状を伝えることが大切
非器質性の精神障害は、症状を裏付ける客観的証拠が乏しいことから、状況証拠がとても大切になります。
たとえば、事故から一定の時間が経過してから初めて受診した場合や症状を伝えることが遅れることにより、事故と症状との間の相当因果関係が否定されてしまうことがあります。
できる限り早期に受診し、早期に症状を伝えることが大切です。
4 定期的な通院が大切
通院の間隔が長期間空いてしまうと、症状の一貫性、継続性が認められず、後遺障害の認定で不利になることがあります。
症状が一貫していること、継続していることを証明するためにも、定期的に通院することが大切です。
後遺障害が認定されない場合のQ&A 高次脳機能障害となり働けなくなった場合のQ&A