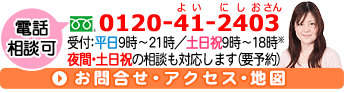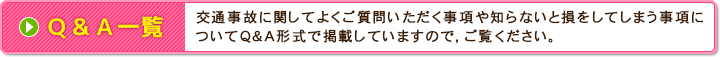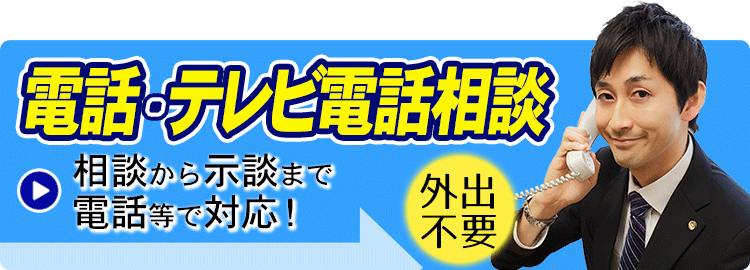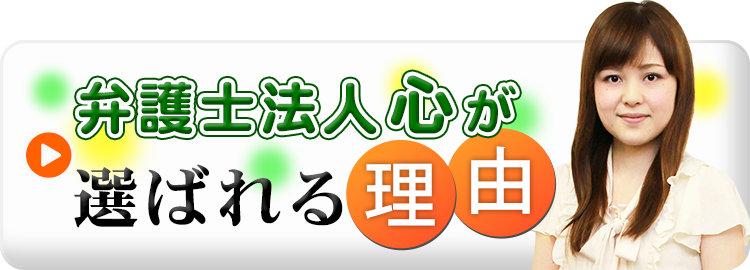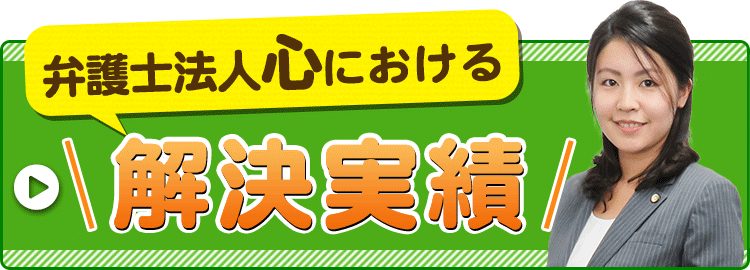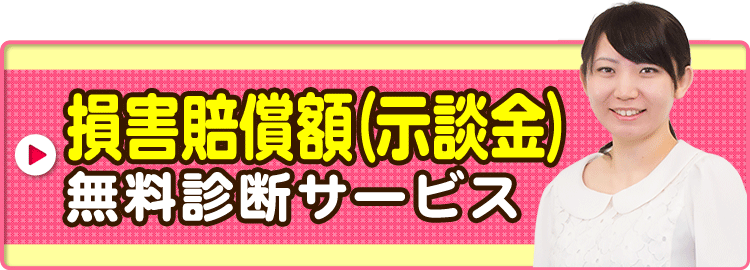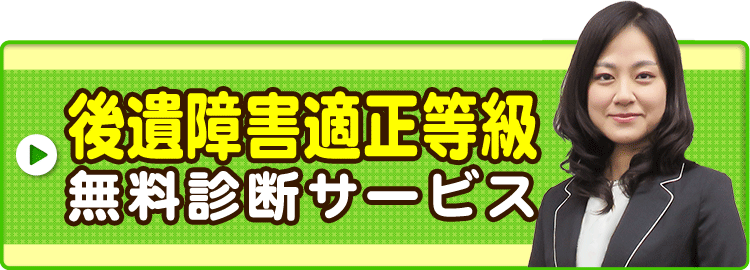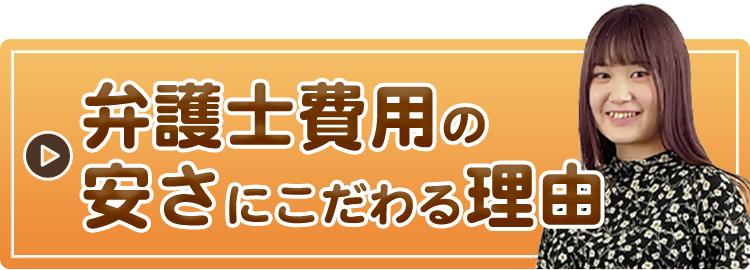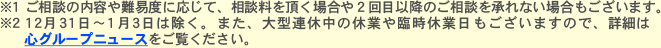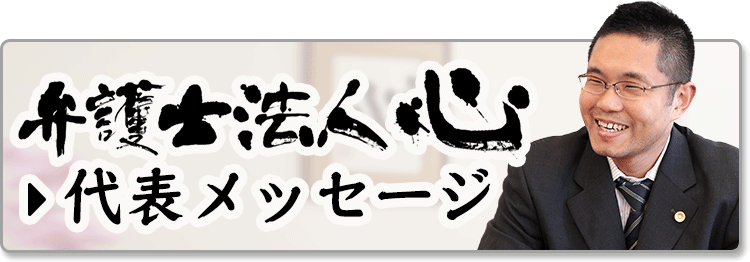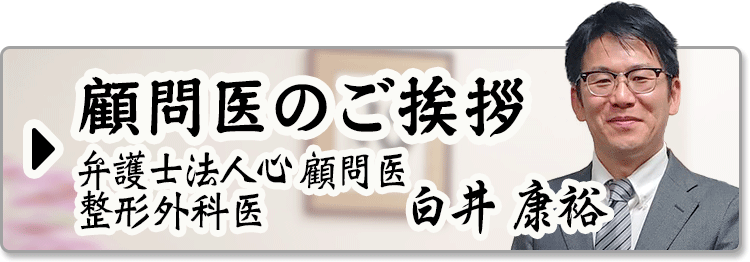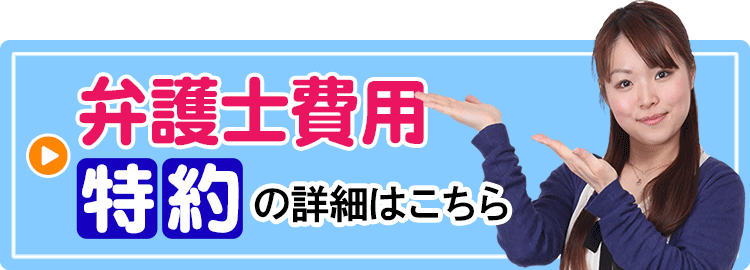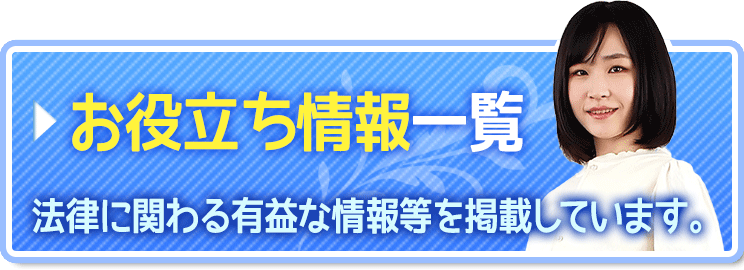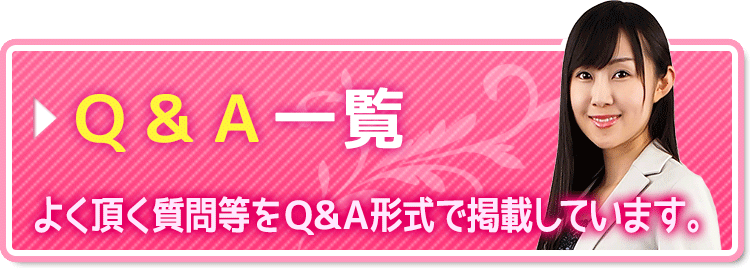個人事業主の休業損害
1 休業損害について
休業損害は、事故により仕事ができなかったことによる損害をいいます。
入院したりケガの影響で働くことができなかったりしたことで収入が減少した際は、休業損害として加害者側に請求することが可能です。
2 サラリーマンと個人事業主の違い
給与所得者であるサラリーマンの場合、職務・勤務に要した経費は、会社が負担してくれるため、事故の影響により仕事を休んだとしても、通常、休んだ期間中に、経費の出費がかかることはありません。
他方、個人事業主の場合、事故の影響により仕事を休んでいる期間も、事務所の家賃や従業員の人件費などが発生します。
つまり、休業期間中でも経費を負担しなければなりません。
3 個人事業主の休業損害に対する考え方
交通事故被害者の加害者に対する請求権は、法律的には、不法行為に基づく損害賠償請求権といいます。
不法行為に基づく損害賠償請求権の制度趣旨は、損害の公平な分担にあります。
個人事業主の方の経費が補填されないとすれば、損害の公平な分担が実現されません。
そのため、一定の範囲で経費を含めた金額で休業損害を算出することが正しい形になります。
4 休業損害の基礎収入に含まれる経費はどのようなものか
個人事業主の休業損害を計算するための基礎となるものとして、所得額が含まれることはもちろんですが、所得額に加えて固定経費も基礎に含まれます。
一方で、変動経費は含まれません。
例えば、租税公課、損害保険料、利子割引料、地代家賃、諸会費、リース料などを固定経費として基礎に含めた裁判例(大阪地判平成9年7月29日)や、保険外交員の事例について、租税公課、水道光熱費、通信費、損害保険料率、修繕費、減価償却費、地代家賃、諸会費、研修費、販売促進費、会社控除、支払手数料、接待交際費のうち冠婚葬祭費、慶弔費、お見舞い金、お歳暮・お中元の贈り物は固定経費として基礎に含めた裁判例(東京地判平成23年1月26日)があります。
このように、職種や状況に応じて休業損害の基礎に含まれる経費は様々です。
5 個人事業主の休業損害を弁護士に相談するメリット
交通事故被害に遭われた個人事業主の方が、休業損害に経費を含めることができると分かっても、ご自身で保険会社の担当者と交渉することは簡単ではありません。
保険会社の担当者は、日常的に交通事故事件を取り扱っていますが、被害者の方にとって、交通事故被害は一生に一度あるかないかの非日常な出来事です。
そのため、どうしても事故に関する知識量には差があります。
保険会社とのやり取りを負担に感じる方もいらっしゃるかと思います。
交通事故の問題に関する知識が豊富な保険会社の担当者の方と対等に渡り合うには、ご自身で交渉するよりも、交通事故を得意とする弁護士に任せた方が、ご自身にとって、精神的にも経済的にも良い方向に向かうのではないかと思います。
保険会社は、個人事業主の休業損害について固定経費を含めずに、所得額のみを基礎収入として休業損害を算出した示談金を提案することも少なくありません。
職種や状況に応じて固定経費となるものは変わりうるものですので、お悩みの方は、お気軽に当法人の弁護士にご相談ください。
交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が相談をお受けいたします。
交通事故における弁護士基準での慰謝料 後遺障害申請の事前認定と被害者請求